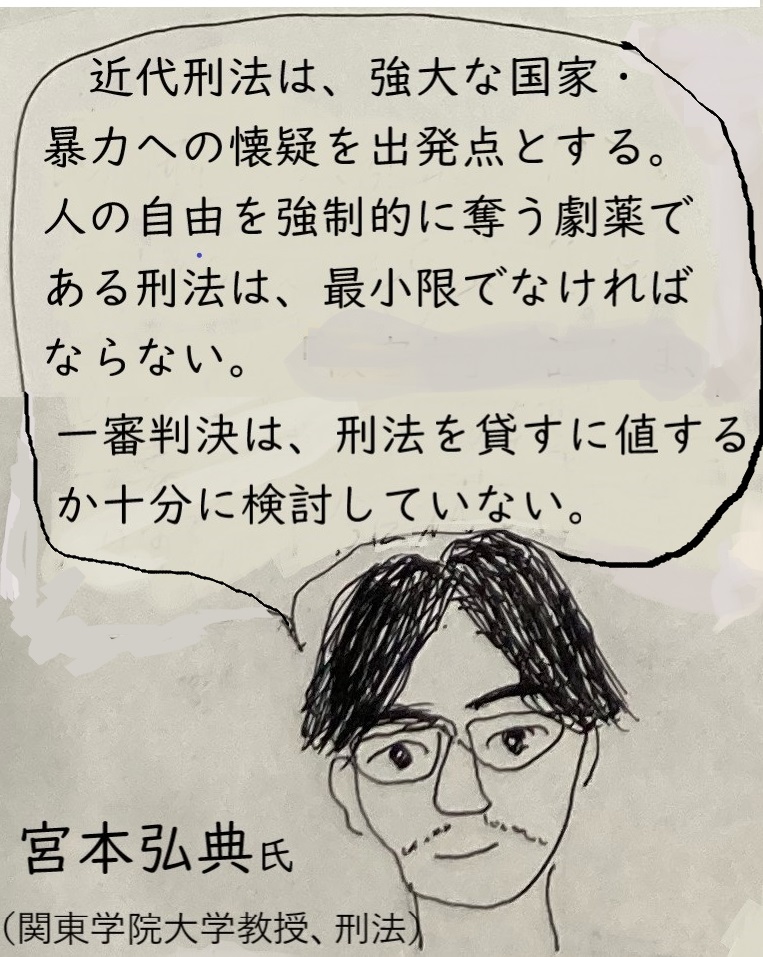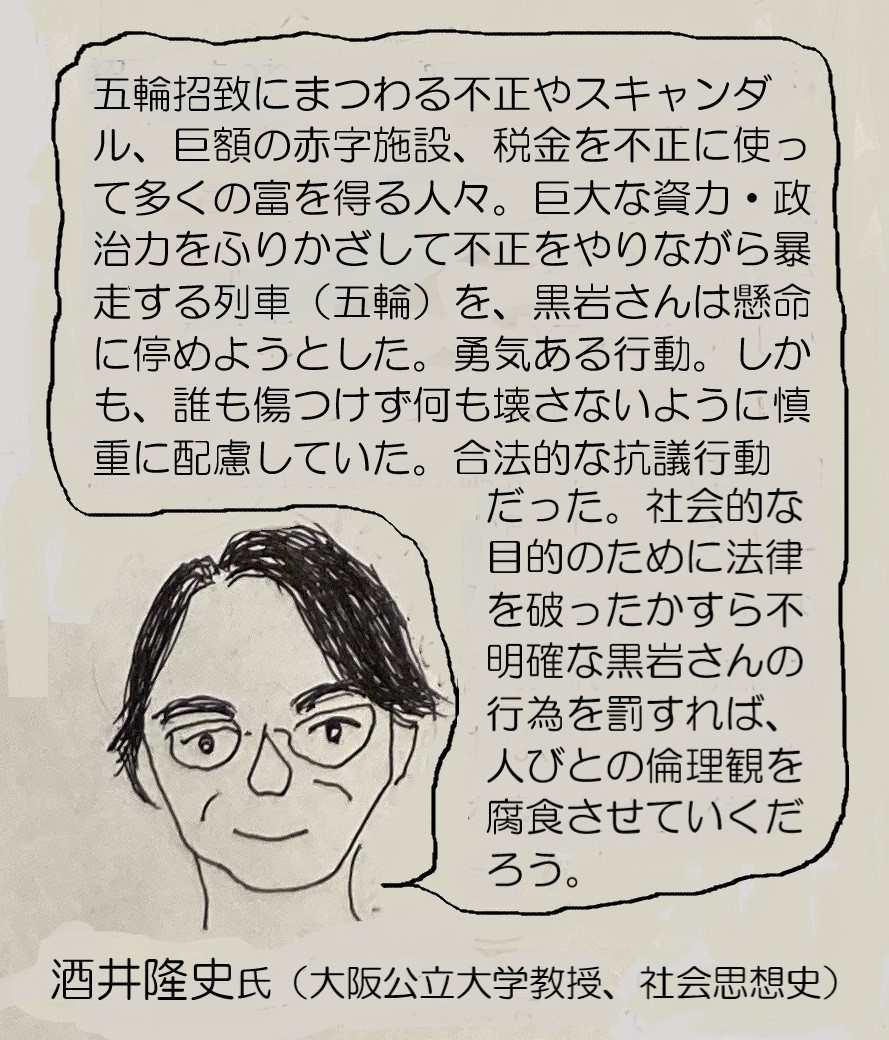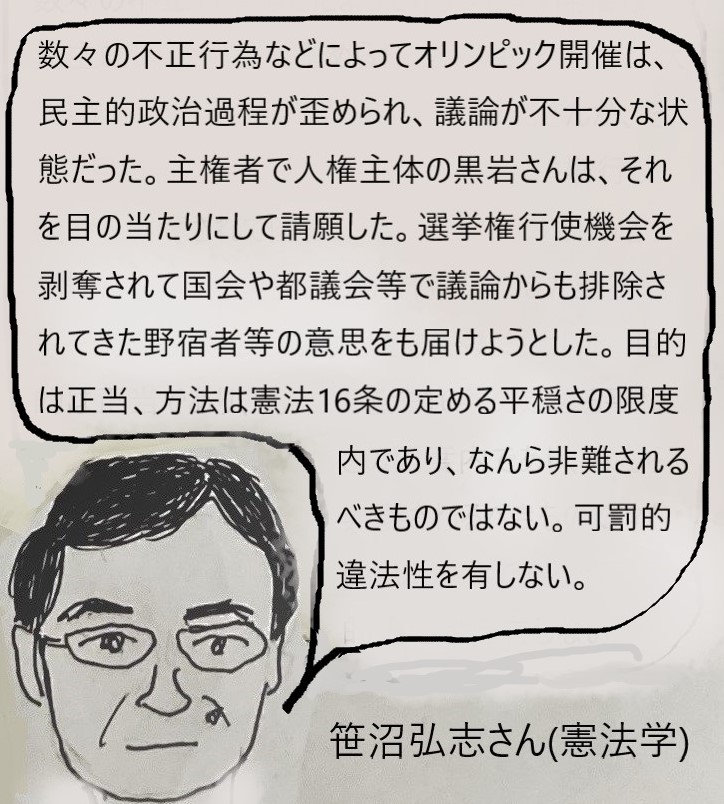- [:contents]
- はじめに
- 第1 事実の誤認
- 第2 法令適用の誤りその1~被告人の行為は刑法234条の構成要件に該当しない
- 3 被告人の行為は「業務を妨害」していない
- 4 構成要件該当性は認められない
- 第3 法令適用の誤りその2~被告人の本件行為は違法性が阻却される
- 第4 結語
威力業務妨害被告事件
被 告 人 黒 岩 大 助
弁論要旨
2024年5月28日
弁護人 栗 山 れい子
弁護人 山 本 志 都
弁護人 石 井 光 太
弁護人(主任) 吉 田 哲 也
頭書被告事件について、弁護人栗山れい子、同山本志都、同石井光太、同吉田哲也の弁論の要旨は以下のとおりである。
はじめに
2024年2月28日付弁護人ら作成に係る控訴趣意書、同日付被告人作成に係る控訴趣意書、同年11月28日付「検察官答弁書に対する反論」に加え、弁護人らは本書面において、当審において実施された事実の取調べに基づき以下のとおり弁論を行う。
第1 事実の誤認
1 被告人の行為により退場が20分間遅延したという事実誤認について
⑴ 原判決は、「Uは、本件イベントの会場から退場しようとする参加者等を引き留めておくようスタッフらに指示し・・・・その結果、退場しようとする参加者を20分くらいの間、やむを得ず待機させた」と認定している(原判決の4頁)。
⑵ しかし、同認定の根拠となるU証人の「20分ぐらいは待たせた」という証言は、曖昧かつ取ってつけたようなものであり、また、本件現場付近を撮影した映像(甲16)において確認できる最終退場者の退場時刻と予定されていたイベント終了時刻の差は6分程度に過ぎずないことなどから、信用性に欠けるものであることは、既に控訴趣意書において指摘したとおりである。
⑶ これに加え、本件で採用された松下玲子武蔵野市長(本件イベントに参加)の回答書(当審、弁1)によれば、本件発生後、「ルート変更せず、体育館正面から退出した。担当者から退出を待つ指示は受けていない。」「退出を待つ指示は受けていないが、正面の出入り口には警察官や機動隊員などが多数集まっていたため、退出に若干時間はかかった。」というものである。
甲16の映像によれば松下市長が体育館敷地から退場した時刻は17時19分14秒であるが、松下市長は、担当者から退出を待つよう指示を受けていないし、警察官や機動隊員の存在により現場の通過に若干の時間を要したものの、退出まで20分といった長い時間を要したわけではない。
⑶ 原判決は、信用性に欠けるU証人の証言に依拠して、「20分ぐらい待たせた」という事実認定を行っているが、その認定は誤りである。
2 柵を乗り越えようとした行為の態様に関する事実誤認について
⑴ 原判決は、「被告人は・・・警備関係者らの制止を振り切り、同バリケードを乗り越えて同敷地内に侵入しようとし」たと認定している。
⑵ しかし、甲16の映像によれば、被告人がバリケードを乗り越えようとする行為に入る前にU証人ら警備関係者から制止を受けていないことは明白であり、「制止を振り切り・・・バリケードを乗り越えようとした」事実がないことは、控訴趣意書で指摘したとおりである。
⑶ 加えて、当審における被告人は、「バリケードの向こう側に爆竹を放り投げた先に人はいなかった」「バリケードを乗り越えようとしたとき、バリケードの向こう側に人はいなかった」「警察官に取り押さえられた、押し戻されるような形で逮捕された。敷地外に引き戻されて逮捕された」と供述しており(当審の第2回公判調書)、バリケードを挟んだ体育館敷地内に人はいなかったのであり、被告人はバリケードを乗り越えようとする前に警備関係者から制止を受けた事実はない。
3 以上のとおり、原判決には事実の誤認がある。
第2 法令適用の誤りその1~被告人の行為は刑法234条の構成要件に該当しない
原審は、刑法234条の構成要件に該当しない被告人の行為を、業務妨害罪の構成要件に該当するとするものであって、法令の適用を誤り、その誤りが判決に影響を及ぼすものであることは明らかである。
控訴審で証拠採用された宮本弘典教授の「過度に広汎な処罰の禁止と刑法上の違法性~いわゆる『武蔵野爆竹事件』における威力業務妨害罪の成否をめぐって」(当審、弁2。以下「宮本意見書」という)は、本件の原審において、構成要件該当性の判断として、①爆竹を1回点火するなどの被告人の行為が「威力」に該当するか(威力業務妨害罪を適用して刑罰を科すに値するだけの違法性の質と量を具備する行為であるか)、②被告人の行為によって、活動の自由の放棄・断念に至らしめる結果(の抽象的危険)が発生しているか、という点について、刑罰法規適正の原則から導かれる「過度に広汎な処罰の禁止」に反する刑罰法規適用という帰結に至っていることを指摘し、原判決は破棄を免れないとの結論に至る。
本章では、主に宮本意見書を参照しながら、被告人の行為に構成要件該当性が認められないことを主張する。
1 構成要件該当性を判断する際に考慮すべき内容
⑴ 「威力業務妨害罪」の成立範囲に対する一定の歯止めの必要性
業務妨害罪について、「威力」は「人の意思を制圧するに足りる勢力を使用すること」とされるが、仮に、威力は必ずしも直接現に業務に従事している他人に加えられることを要しない、業務遂行者の身体に対する直接的な危害を及ぼす情況を要しない、現実に被害者が自由意思を抑圧されることを要しないなどという立場に立てば、その「威力」の成立範囲はきわめて広汎になる。また、「業務を妨害した」について、現実の妨害結果の発生を要しないとすれば、構成要件的結果発生によって犯罪の成立範囲を画することは不可能となる(宮本意見書の4~5頁)
業務妨害罪の構成要件該当性がこれだけ融通無碍に拡張されているのは、本罪が社会活動の自由一般に対する侵害行為を広く包摂するものと解されるためと思われる。したがって逆に、業務妨害行為の外延の拡大・拡散によって、基本権行使を含む自由な活動が広く本罪の構成要件に包摂される事態に対して、一定の歯止めを設けることが必要になる。
本件原審でも展開したように、威力業務妨害罪の構成要件該当性が認められるとしても違法性が阻却されるという解釈は、このような必要性に基づき行われてきた。典型的には、労働基本権の行使などの場面である。
もちろん、本件のように政治的な意思表明が犯罪に擬せられた場合に、表現活動に対する刑事規制を排除するために、表現の自由を保障する憲法21条など人権規定を対置させて違法性阻却あるいは正当行為の問題として解釈することは重要でありかつ適切でもある。ただ、「表現そのものを処罰することの憲法適合性」ではなく「表現の手段を処罰することの憲法適合性」が問題にされるのであれば、別の手段を選択しえたにもかかわらず当該行為に及んだ点をとりあげて行為態様が相当性を欠くという結論になって違法性が肯定されることにつながりやすい。
しかし、業務妨害罪のような一般的な刑罰法令が市民的自由を制約するために用いられている場合、違法性判断の前に、そもそも、このような行為に刑罰法規の適用が許されるのかということが問題にされなければならない。基本権行使に対して刑罰法規が適用されることが一般化され、国家刑罰権が市民の日常生活の隅々にまで浸透してしまえば、それは実際には市民の基本権行使を直接に侵害するものとなり、自由主義を後退させることに直結するからである。
⑵ 刑罰法規の適用段階における必要性・相当性の要求
ア 近代刑法の自由保障機能
刑罰法規は、生命・自由・財産という基本権剥奪ないし制限を担保として、社会的利害を調整し、一定の規範条件に向けてその統合を図るという意味で、国家が独占的に行使する実力装置として機能する。
しかし、その一方で、近代刑法は、国家による自由の抑圧・侵害という歴史の教訓に学んだ、強大な国家権力への徹底的な懐疑が出発点にある。近代国家が、物理的な実力(暴力、権力)を、排他的かつ組織的に所有し行使するものとして存在する以上、近代刑法の目的は、積極的・包括的な社会防衛手段の発動ではなく、むしろ、国家が独占する強大な刑罰権から個人の自由を保護することにある(宮本意見書13頁)。
このような近代刑法の自由保障機能に注目するとき、刑法の適用は謙抑的であるべきという原則が導かれ、刑法上の違法性は単に当該行為と結果が形式的に構成要件を充足することだけで認められるべきではなく、刑罰を科すに値するだけの質と量を持つものでなければならないことになる。
刑事法・行政法・民事法といった各法領域は、その自由侵害の程度と強制力に応じて各法領域に特有な違法性の質と量を有するから、違法の発現は各法領域によって異なることになる。一方で、違法阻却の基準は各法領域を通じて統一的に解され、自由侵害の程度と強制力のより微弱な法領域における違法性が認められない行為については、より強大な法領域における違法性もまた認められない(ソフトな違法一元論、宮本意見書14頁)。
刑法は強制的に自由や財産、生命を剥奪する法領域であり、自由侵害の程度と強制力において、法の最大限に位置する。刑罰という制裁は強力で副作用を伴うものであるから、何を刑法の対象とするかの判断にあたっては、本当に刑罰をもって抑止する必要のある行為か否かについて慎重に判断する必要がある。刑法上の違法性は、単に当該行為と結果が形式的に構成要件を充足するというだけでは足りず、刑罰を科すに値するだけの質と量を持つものでなくてはならない。そして、行政法や民事法との関係でいえば、行政法領域や民事法領域において違法であるからといって、それが刑法上の違法性を有するわけではなく、逆に、行政法領域や民事法領域において違法性が認められない行為については、刑法上の違法性も認めることはできない(宮本意見書14頁)。
実際に、刑法は、たとえ、重要な法益侵害があってもその全てを刑罰の対象とはしていない。通常の債務不履行のように民事賠償にまかせれば足りるものや、免許の停止や取消しなどの行政処分で制裁として十分であるものについて、あえて刑罰は科されていない。
イ 過度に広汎な刑事規制の禁止
上記のような刑法の機能から導かれる「刑法の謙抑性」は、日本国憲法上「罪刑法定主義」の原則と連結するものと解することができる。その内容を展開すれば以下のとおりとなる。
近代刑法は、「法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし」という、罪刑法定主義の原則を基本に持つ。ある行為が当罰性を有しているからといって、それだけで勝手に処分できるとしたら、権力者は自分に都合の悪い人間を処罰することができ、市民の自由はまったく害されてしまうからである。
同原則は、自由主義の原理と民主主義の原理から成り立つ。自由主義の原理は、国民の自由を確保するために、犯罪と刑罰の内容があらかじめ国民に告知されていなければならないという考え方であり、マグナ・カルタ以来の人権宣言に採用されてきた。民主主義の原理は、国民を処罰する刑罰法規は、主権者たる国民の代表である議会を通じてのみ決定されなければならないという考え方であり、三権分立の理論の帰結でもあった。
憲法31条は「法律の定める手続」によらなければ、生命・自由を奪われまたはその他の刑罰を科せられないことを保障する。この規定は、基本的に、国家の刑罰権が市民の人身の自由に対する重大な脅威となるものであるため、法律によってその手続を定め、恣意的な刑罰権の発動を抑えようとするものである。
そしてここにいう「法律の定める手続」には、犯罪を認定して刑罰を科す手続である刑事訴訟を規律する手続法のみならず、その前提となる実体要件、刑罰権発動の根拠たる実体法も含まれると解されている。なぜなら、憲法が人間の尊厳に基づく自由と民主主義原理の実現を保障するものであるとすれば、基本権に対する暴力的制限を装備する刑罰法規について、相応の実体的内容の適正が求められるのは当然だからである。20世紀前半期、形式的合法性を充足する法律が市民の日常的な自由を奪い取ったファシズムの歴史もその必要性を裏づける。
そして、人間の尊厳を根拠とする基本権実現こそが公共的正義の理念となるのだから、原理的問題を政策的合理性や合目的性に譲歩させてはならないという判断もここから導かれる。
吉川経夫は、罪刑法定主義原則を堅持することの重要性について以下のとおり述べた。「罪刑法定主義は、日本国憲法によって再確認された。しかし、これを憲法における抽象的な宣言にとどまらせては無意味である。先にみたように、国民によって闘い取られた歴史をもたないわが国の罪刑法定主義は、支配階級によってつねに形骸化されようとする危険をはらんできた。しかし、現在の時点においてこの形骸化を許すことは、国家権力の専権から国民の民主主義的自由と権利を守るための最後の防塁を奪い去られることを意味する。施行後、日なお浅い日本国憲法のもとでの民主主義を、ナチズムやファシズムの反動から守るためには、国民ひとりひとりの抵抗によって、罪刑法定主義の原則を維持しなければならない。」罪刑法定主義は、実質的デュー・プロセスの原則をその内容とすることによって、国家権力から個人の人権を守る原理として非常に重要な盾となるという指摘である。
(イ)明確性の原則及び刑罰法規の適正の要請
罪刑法定主義からは、法律主義、事後法の禁止、類推解釈の禁止、明確性の原則、刑罰法規の適正という、派生原理が導かれるとされる。このうち、本件における構成要件該当性の判断と関連するのは、明確性の原則と刑罰法規の適正の要請である。
何が禁止されている行為であるかを国民が容易に判断できないような刑罰法規は、国民の行動の予測可能性を奪うことになり、その行動を萎縮させることになるから刑罰法規は明確でなくてはならない。これが「明確性の原則」である。
最高裁も理論としてはこの原則を肯定している。デモ行進の許可条件である「交通秩序を維持すること」という文言が不明確のゆえに無効か否かが争われた徳島市公安条例事件において、「ある刑罰法規があいまい不明確のゆえに憲法31条に違反するものと認めるべきかどうかは、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れるかどうかによってこれを決定すべきである」と判示した(最大判1975年9月10日)。
さらに、その処罰範囲において明らかに当罰的ではないものを含んでいる場合には、刑罰法規の適正さに欠け、罪刑法定主義に反すると言わなければならない。
福岡県青少年保護育成条例の「淫行」の解釈について、最高裁は、「広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、・・例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものを含むことになって、その解釈は広きに失することが明らかである」として、「淫行」概念を「青少年を誘惑し、曰くし、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解するのが相当である」として、限定的に解釈した(最大判1985年10月23日)。これは、「淫行」という文言のままでは、処罰範囲が不当に広くなって罪刑法定主義に抵触するとの判断が前提にあったと評価することが可能である。
(ウ)過度に広汎な処罰の禁止
罪刑法定主義原則による刑罰法規適正の原則は、刑罰法規の創設段階における必要性・相当性を要請する「過度に広汎な刑事規制の禁止」のみならず、その適用段階における必要性・相当性の要求である「過度に広汎な処罰の禁止」をも包含する(宮本意見書19頁)。これは、前述したソフトな違法一元論とも親和的である。
基本権行使の性質を有する行為について、「過度に広汎な処罰の禁止」原則に適応すべく、法規を合憲的に限定解釈し、実質的には、刑罰を科すに値するだけの質と量を有する刑法上の違法性を具備しないとして、刑罰法規の適用を否定したとみることができる判例が存在する。以下、宮本意見書に従い3例を紹介する(20~22頁)。
HS式無熱高周波療法を業として行ったことが、旧あん摩師、はり師、きゅう師及び柔道整復師法12条が禁止する、業として行う「医業類似行為」にあたり、処罰の対象となるかが問題となった事案において、最高裁は、憲法22条の職業選択の自由は公共の福祉に反しない限り保障されるから、公共の福祉に反する医療類似行為に処罰は限定されなければならないとする立場から、処罰の対象となるのは、「人の健康に害を及ぼす虞のある業務行為」に限られるとして、無害な行為を処罰することは許されないという合憲限定解釈を行っている(最大判1960年1月27日)。原判決は、医療類似行為禁止の趣旨を、積極的に人体に危害を生ぜしめる場合もあり、そうでなくても人をして正当な医療を受ける機会を失わせ、疾病の治療回復の時期を遅らせるおそれがあるとして、処罰の対象となるとして有罪とした。最高裁は、より積極的な害の発生を要求し、無害の行為であれば刑罰法規を適用することは刑罰法規適正の原則に反するという前提に立っているものと評価できる。
最高裁は、1967年7月20日、破壊活動防止法38条2項2号の、内乱の目的をもって内乱の「実行の正当性又は必要性を主張した文書」を頒布する罪は、「右文書の頒布により内乱罪の実行されうべき可能性ないし蓋然性が客観的に存在していたことは認められない」事案については成立しないと判示した。当該行為は内乱文書頒布の刑罰法規を適用し、刑罰を科すに値するだけの違法性の質と量を具備していないという判断が行われている。
さらに、最高裁は、1969年4月2日、いわゆる都教組事件において、「二重の絞り論」を展開し、以下のとおり、限定解釈による刑罰法規適用の縮減を試みている。「地公法61条4号は……争議行為自体が違法性の強いものであることを前提とし、そのような違法な争議行為等のあおり行為等であってはじめて、刑事罰をもってのぞむ違法性を認めようとする趣旨と解すべきであって、……あおり行為等の対象となるべき違法な争議行為が存しない以上、地公法61条4号が適用される余地はないと解すべきである。……さらに進んで考えると、争議行為そのものに種々の態様があり、その違法性が認められる場合にも、その強弱に程度の差があるように、あおり行為等にもさまざまの態様があり、……その違法性の程度には強弱さまざまのものがありうる。それにもかかわらず、これらのニユアンスを一切否定して一律にあおり行為等を刑事罰をもってのぞむ違法性があるものと断定することは許されないというべきである。ことに、……地公法61条4号の趣旨からいっても、争議行為に通常随伴して行なわれる行為のごときは、処罰の対象とされるべきものではない。……したがって、職員団体の構成員たる職員のした行為が、たとえ、あおり行為的な要素をあわせもつとしても、それは、原則として、刑事罰をもってのぞむ違法性を有するものとはいえないというべきである。」これは、行政法上違法とされ懲戒対象とされる争議あおり行為であっても、更に強度な質と量を具備する違法性が認められない限り、当該行為について刑法上の違法性を否定せねばならないという判旨である。
「過度に広汎な処罰の禁止」は、最高裁も判断の前提におくものといってよい。
2 被告人の行為は「威力」とは認められない
⑴ 表現の自由としての側面
原判決も認めるように、被告人の行為は表現の自由の行使という側面を有する(後述するように、被告人の行為には請願権の行使という側面もある)。
そして、上記「過度に広汎な処罰の禁止」の自由保障機能に鑑みるとき、そのような優越的な保護を必要とする基本権の行使に対する刑罰権の行使が問題となる場合には、違法性判断にとって積極的な事実のみならず、消極的な事実も全て拾い上げて考慮して、なお、当該行為に対する刑罰法規適用が肯定されるか否かが検討されなければならない(宮本意見書23頁)。
しかし、原審は、被告人の行為を「表現行為」であるとしながら、被告人の行為の構成要件該当性を判断するに際して、単に形式的に構成要件該当性を検討するのみで、被告人の行為の違法性を低減するような事実を、弁護人らの指摘にもかかわらず、一切無視した。原審は、基本権行使に対する刑罰法規適用の検討において、全く不十分というほかない。
⑵ 「威力」非該当
「威力」該当性について検討すべき要素については、原審でも控訴趣意書でも詳細に述べたところであり、ここでは繰り返さない。
ア 威力業務妨害罪に必要な「威力」の程度
学者の見解を参考にすれば、行為時誰もいなかった工場の配電室のスイッチを切断する行為について、威圧的要素がないから本罪の成立を認めるのは妥当ではないという批判があり(平野龍一『刑法概説』1977年)、「威力」該当性を肯定するには、単に公然となされたといっただけでは足りず、実力による排除を困難ならしめるような威圧感を与えることが必要とすべきとの見解がある(中山研一『刑法各論』1984年)。
争議時の行為が威力業務妨害に該当するか否かが問題になったケースで、「刑法第234条にいわゆる威力とは有形たると無形たるとを問わず、犯人の権勢員数及び四囲の事情により他人の意思を抑圧する勢力を指称するのであるがそれが威力と称しうる程度かどうかを判断するに当つては相手方の身分やそれが行われた時と場所の関係をも考慮に入れて考えなければならない。検事は被告人が司法警察員に対する第一回供述調書で仕事をやめろなどと大声を出したことはおぼえていると述べているので被告人が正当な争議行為の範囲を逸脱したと主張するが、争議中の労働者の言動に手荒なことのあるのは争議の性質上極めてありがちなことであるから被告人に右のような言動があつたとて直ちに争議行為の範囲を逸脱したとはいえない。争議中の労働者の言動が手荒であつたからとて直ちに威力に該当することになれば労働争議はたやすく弾圧され争議権は骨抜きとなるであろう。もとより労働争議が当事者双方の節度を重んずる態度によつて行われることは望ましいことであるが極めて困難なことである。従つて手荒な労働者の言動が威力といえるかどうかは諸般の事情によつて決しなければならない。記録につき当時の事情を調査してみると原審証人S、Iの証言によれば被告人等争議中の組合員が工場に入つて来たのは正午前頃であつて、当時その工場は脱退組合員や臨時工員で操業中であつたこと即ちその場所は被告人等のもとの職場であり且つ『作業を止めろ』といわれた相手方は被告人等のもとの同僚工員であり脱退組合員であつたこと、及び原判決も説明している如く争議組合員等の当時の行動自体比較的静粛であつたこと等の事情を綜合すると被告人の本件言動はいまだ刑法にいわゆる威力の程度に達していなかつたものと認められる」(大阪高判1951年2月9日)と威力該当性が否定された裁判例もこのような見解に立つものといえる。
イ 被告人の行為へのあてはめ
被告人は、①誰も傷つけず、②一方で明確に抗議の意思表示であることを示すことができ、③目立ち、④入手が容易で、⑤安価であることから、単独で行う表現方法として、適切かつ妥当であると考えて、爆竹を選択している。①ないし⑤の特性は客観的にも肯認できるから、被告人が爆竹を今回の表現方法として選択したことには、合理性が認められる。
その上で、「爆竹の使用という事実―そしてその爆発によって意思を制圧され、業務妨害結果が発生した、あるいは発生する(抽象的)危険があったという認定―をもって、直ちに被告人の表現「手段」が「相当性」を欠くという帰結を導くことはできない。」宮本意見書が掲げるように、①爆竹は種々のイベント等にも使用に供される日常品でそれ自体とくに危険物ではないこと、②爆竹の使用が本件イベント終了予定時刻を10分以上経過した後であること、③使用した爆竹の量も到底大量とは認められないこと、④爆竹の使用(点火)は1回のみで複数回にわたって執拗に繰返されたものではないこと、⑤被告人は爆竹を会場に隣接する「体育館敷地内」に投げ入れたのであって、沖縄返還協定に反対して議場内で爆竹を鳴らしたという東京地判1973年9月6日の事案とは異なり、イベント会場である競技場内で使用したものではないこと、⑥国家的イベントへの対抗手段として大きな非対称性が認められることなどを考慮すれば、威力業務妨害罪としての処罰に値するだけの量と質の違法性を有するとは認められず、到底「威力」とは評価しえない。
3 被告人の行為は「業務を妨害」していない
⑴ 侵害犯と解する多くの学説の存在
威力業務妨害の構成要件的結果について、判例は、妨害の結果を発生させるおそれのある行為をすれば足り、現実に妨害の結果が生じたことは必要ではない、という立場であると整理される。しかし、近時の学者の見解を確認してみると、現実の結果発生を要する侵害犯と解する立場が多いといえる。
小野清一郎『新訂刑法講義各論(第3版)』1950年、滝川幸辰『刑法各論(増補版)』1951年、平野龍一『刑法概説』1977年というのが過去の有力説である。そして、「本罪を危険犯とすることは、もともと広すぎる本罪の処罰範囲をさらに広げるもので、妥当ではない」という本章冒頭で提起したのと同様の問題意識を共通にして、①刑法234条の文言が「業務を妨害した」ことを求めていることから、危険犯との解釈には法文上何らの根拠もなく、妨害行為と妨害の結果との間に因果関係がなければ、未遂の処罰規定がない以上、不可罰となるのはむしろ当然の帰結である、②現行刑法の業務妨害罪の位置づけは「業務活動の自由」に対する罪であり、そのような「自由」を保護法益と考える限り、他の自由侵害犯と異なる扱いをする必要はなく、業務の運営が実際に害されるという結果の発生が必要となる、③業務活動の自由の「侵害」は、名誉や信用毀損の結果と異なり、認定に格別の困難はないなどの理由から、近時は、侵害犯と解する見解が相当に多い(中山研一『刑法各論』1984年、平川宗信『刑法各論』1995年、内田文昭『刑法各論』(第3版)1996年、山中敬一『刑法各論Ⅰ』2004年、岡野光雄『刑法要説各論(第5版)』2009年、斎藤信治『刑法各論(第4版)』2014年、中森喜彦『刑法各論(第4版)』2015年、西田典之『刑法各論(第7版)』2018年、大谷實『刑法講義各論(新版第5版)』2019年、高橋則夫『刑法各論(第4版)』2022年など)。
⑵ 証人Uの業務は妨害されていない
証人Uが業務遂行に著しく困難を覚え、あるいは断念せねばならないほどに意思を制圧され、現にそれによって請負った上記の業務を遂行し得なかったという結果が発生していなければ、構成要件的結果の存在を認めることはできない。
原判決は、現に発生していない事実である、「証人Uらの……火傷」や「被告人と証人Uらが接触して転倒したりする危険」に加えて、やはり「更に激しい爆発」や「複数人による同様の行為」の可能性という「虚構」を根拠として、証人Uらが感じる可能性があった「恐怖」を増幅して認定した。
また、証拠に基づかず、「実際の業務にも少なからず支障が生じ」たとした。
本来裁判所が検討しなければならなかったのは、事実として認定されている被告人の行為によっていかなる結果が生じたのか、という点である。威力業務妨害罪の成立を肯定するには、証人Uの本件イベント業務遂行の放棄・断念という結果を要するはずだが、原審はこの点について正確な事実関係を認定することなく業務妨害の結果発生を肯定してしまった。
①本件イベントそれ自体はほぼ予定どおり行われたこと、②証人Uの反応は、「多分ちょっと僕も一瞬びくって、びっくりはしたんだと思います」という程度のものであったこと、③本件発生後に市長など警備・警護を要する者が退場していることから、緊迫した状況は生じていなかったことなどの事情からすれば、威力業務妨害罪に必要とされる質と量の業務妨害の結果は生じていない(宮本意見書25~26頁)。
⑶ 証人Uは保護されるべき「業務」の主体ではない
判例は、いわば「結果としての業務妨害」が存する限り本罪の成立を肯定しており、本罪は端的に「業務の円滑な遂行」を保護するものとなっている(その結果、偽計と威力の区別も本質的な意義を失い、単に業務妨害の手段が公然か被公然かという差異でしかなくなってしまっている)。しかし、本罪を業務活動の自由に対する罪と捉えれば、偽計、威力は人の意思に対する働きかけでなければならない。そして、被告人の意図は、本件イベントそれ自体の阻止・妨害ではなく、東京オリパラ及びそれに関連するイベントへの反対意思の表明という点にあった。そう考えれば、そもそも、証人Uの業務遂行の放棄・断念を業務妨害罪の結果とすることの是非が検討されねばならない。
被告人の意図からすれば、関連イベントに対する抗議は意思表示の手段である。仮に、イベントに関わる証人Uのようなイベント会社社員の業務遂行等を阻止・妨害したとして業務妨害罪の罪責を問うとすれば、当該イベントそれ自体の催行の―内容・日程等の大幅な変更を含む―放棄・断念という結果が発生したか否かにかかわらず、その因果のプロセスのいずれかの段階を切取って業務妨害罪を適用し得ることになる。現に本件は、本件イベント自体の催行を妨害し阻止したとは認め難いとして、証人Uに対する業務妨害罪で起訴され有罪とされたのであろう。
こうした因果の流れの上に生じた個別の事実―強要・脅迫、住居侵入、逮捕・監禁、業務妨害等々の構成要件の形式的な充足―を切取って、当該行為(及び結果)の違法性を認定するという機会主義的・便宜主義的な刑罰法規適用は、刑罰法規適用の機会を増大させるという点で、すくなくとも刑法の謙抑性・断片性・補充性という近代刑法の不可欠な前提をなす公理に背反し、その限りでその実践原理である罪刑法定の原則―の趣旨―にも反する。
特に基本権行使の側面を有する行為について、このような起訴を行うことは、一般刑法の市民的治安法化を更に促進するものでしかない。それは、市民的自由に対する現実的な脅威を意味し、刑事司法に対する市民の信頼を失わしめるものであって不当というほかない(宮本意見書26~27頁)。
4 構成要件該当性は認められない
原審の構成要件該当性に関する判断は、刑罰法規適正の原則から導かれる「過度に広汎な処罰の禁止」に反する刑罰法規適用という帰結に至っている。被告人の爆竹使用等の行為が「威力」にあたるか、被告人の行為によって業務が妨害されたといえるかについて、原審は、証拠による厳格な証明による事実認定を行っておらず、構成要件該当性に関する判断を誤っている。
第3 法令適用の誤りその2~被告人の本件行為は違法性が阻却される
原審は被告人の行為の違法性について法令の適用を誤ったものであり、被告人の行為は正当行為としてその違法性が阻却されるべきであるから、その誤りが判決に影響を及ぼすものであることは明らかである。
1 被告人の行為は憲法上保障されるものであって、正当な業務行為としてその違法性は阻却される
⑴ 原判決は「被告人が本件行為により表現しようとした思想が政治的な意見であることを十分に踏まえても、本件行為の制限は、表現の自由に対する必要かつ合理的な制限として憲法上是認されるものであって」(原判決8頁ないし9頁)として、被告人の行為の違法性が阻却されることを否定した。
上記のとおり原審は被告人の行為が「政治的な意見」の表明であることを認めたうえで、被告人の行為の違法性判断にあたっては、もっぱら憲法第21条1項の保障を享有するかという見地からのみ論じている。
⑵ しかし、原判決が摘示するとおり「政治的な意見」の表現たる被告人の本件行為は、本件イベントの主催者並びに公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、単に「組織委員会」という。)、東京都、及び国をも名宛人とするものでもあることという点において、人一般を名宛人とする「その他一切の表現の自由」について定める憲法第21条1項の保障を受けるのみならず、同第16条の請願権の保障を受けるものである。
⑶ 請願する権利について、憲法16条は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と定める。
この請願の本質は国家機関の認識を深め、国家機関が間違った行動にでるのを防」ぐことであり(清宮四郎「憲法の理論」有斐閣、1969年373頁)、国家機関等が間違った行動に出ることを防ぐことが請願権の本質的機能である。
2 被告人の本件行為は請願行為である
⑴ 請願法において請願行為は「官公署」に対してなすものとされているところ(同法第3条1項)、本件行為がなされた場所は官公署ではなく、また本件行為で「被害者」とされているUは公務員ではない(もっとも、そもそも被告人の本件行為について上記Uを「被害者」として威力業務妨害罪に問擬することの憲法違反性については本書面「第2」のとおりである)。
しかし憲法第16条は請願権の内容について法律で定める旨を規定しているものでもないのであるし、そもそも請願法において規定された態様でなされるものでなければおよそ憲法上の請願権の保障を受ける請願行為たりえない、とすることはできない。
⑵ 被告人が本件行為をなした場所、すなわち爆竹を投げ入れ、バリケードを乗り越えてその内側に進入しようとした場所は、本件行為当時の直前まで東京2020オリンピックの点火セレモニー(以下、「本件イベント」という。)が開催されていた場所である。
ア 本件イベントは地方公共団体である武蔵野市も主催者であることに加え、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に際して公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(以下、単に「組織委員会」という。)が主催し各都道府県が設置する実行委員会が共催して実施された聖火リレーに直接関連するイベントであり、組織委員会が招待した人物50名が参加するものとされ(原審における弁第3号証の15頁)、また組織委員会のホームページにおいても本件イベント及び被告人による本件行為が記載されていた(同号証の末尾頁)。
イ 組織委員会は同オリンピックの準備と運営を監督する団体として、公益財団法人日本オリンピック委員会と東京都により2014年1月24日に一般財団法人として設立され、2015年1月1日付で公益財団法人となったものである。
ウ そして令和3年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号。以下、単に「特措法」という。)において、内閣に「東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部」が設置され(主任大臣は内閣総織大臣。特措法2条、11条)、上記「本部」は組織委員会に資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができるものとしたうえで(同8条)、組織委員会は国有財産の無償使用を始めとする種々の特権を付与され(同14条ないし15条の2)、国は組織委員会からの要請に応じて国の職員を組織委員会の職員として派遣することができるものとされていた(同第16条及び17条)。
このように2020年東京オリンピック・パラリンピックが「国策」として遂行されたものでありしたがって組織委員会の為すところが公権力の為す国家行為と極めて類似しこれと同視すべきものであるという立法事実が存在するゆえに、特措法はその28条において「組織委員会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす」と定めている。
⑶ア 被告人が本件行為をなした場所は、武蔵野市が主催し、かつ上記のとおり公権力の為す国家行為と極めて類似しこれと同視すべき行為を担う組織委員会の極めて強い関与の下に開催されていた本件イベントの会場である。
したがって同場所において「東京オリンピック・パラリンピックやそれに関連する聖火イベントの開催に抗議するという被告人の思想・考えを示すための表現行為」(原判決8頁)としてなされた本件行為は、人一般を名宛人とする表現行為であると同時に本件イベントの主催者そして組織委員会に対する請願行為という性格を極めて強く帯びるものである。
イ そうであるから被告人の本件行為が正当行為としてその違法性が阻却されるかの検討にあたっては、表現行為一般とは別に、本件行為は請願権の保障を受ける行為、あるいは請願権が保障された趣旨が及ぶ行為であるという見地からの検討を要する。
3 請願行為たる被告人の本件行為は、憲法第16条の保障を受ける正当行為である
⑴ 「平穏」概念の相対性
ア 憲法16条において請願について課される制約は「平穏に」ということのみであるところ、この「平穏に」という条件について、宮澤俊義によれば「請願を行うに際して、暴力を用いたり、暴力的威嚇を用いたりすることなく、の意である」 とされている(宮澤俊義(芦部信喜補訂)「全訂日本国憲法」228頁1988年日本評論社)。
もっとも例えばデモ行進は屋外の路上において、往々にして喧騒の中で行われるものであり大音量のスピーカーなどを使用しつつ行われることも一般的であるところ「大衆的なデモ行進を背景とする請願」は「平穏」なものと解されているのであって(樋口陽一・佐藤幸治・中村睦男・浦部法穂「憲法I 注解法律学全集1」1994年青林書院352-353頁)、そもそも上記の「平穏」は相当な幅をもって理解されている相対的な概念である(弁第4号証の6頁)。
なお上記の「暴力的威嚇」とは恣意的な適用に結び付く漠然とした概念であるから、「何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と規定する憲法第16条の趣旨に鑑みこの「暴力的威嚇」という字面を無条件にそのまま首肯することは不相当であり、同概念は例えば違法な害悪の告知を伴う等の場合を意味するものとして限定して解することが相当である。
イ 請願は、国や地方自治体の諸機関に対してその職務権限に属するあらゆる事項について要望を述べる行為であり、まず当該の国家機関等に請願している事実を認識させる必要がある。そうであるから、例えば大きな騒音につつまれている公共事業の建設現場において、その騒音を止めるか低くして欲しいと求める請願の場合のように、喧騒の中で請願の内容(場合によっては請願をしにやってきたという事実それ自体)を正確に伝えるため一定の大きさの声を出すことが必要であり許容される場合があることは当然である。
憲法16条の「平穏」の程度はこのような必要性との比較で相対的に決せられるものであり、したがって請願の内容を正確に伝えるため、あるいは請願をしているという事実を相手に伝えるために必要な一定の手段をとった場合、それが暴力の行使や害悪の告知を伴わない限りは「平穏」な請願として許容されるべきである。
ウ(ア)請願の沿革は、近代的な議会制度が成立する以前の絶対君主制の時代に遡る。市民に政治参加が認められず、したがってその立場を政治的に反映させる公的な制度が存在しない時代においては。被治者が為政者にお願いするという請願は重要な意味を持っていたのであり、近代的議会制度が成立発展する過程においても、現実の国民の要求を議会や行政機関に訴える手段として請願はなお重要な機能を有していた。
もっとも現代においては、市民は選挙権を有し政党等を通じてその意思を国政に反映させることができるのであって、請願は今日ではかつての請願が有していたような重要な機能は持ちえず、憲法上の権利として認められると同時にその重要性が薄れるという状況にある、と説明されることもある。しかし今日の代議制・議会政は必ずしも市民の意思を十分に反映せず、代議制が閉塞状況に陥ることもしばしば発生するのであるから現代における請願権の存在と意義を再評価する見解が有力となっている(野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利「憲法Ⅰ」(第4版)2006年有斐閣517~518頁)。
(イ) 国家機関等が間違った行為に出ることを防ぐことが請願権の本質的機能であるのだから、国家機関の行為の正当性の根拠である代議制、議会政が閉塞し民主政の過程に機能不全が生じている場合においてこそ、その機能不全を是正すべく憲法上の権利たる請願権を積極的に行使することには極めて重要な意味があるのであり(弁第4号証)、そのような場合において請願の内容を正確に伝えるため、あるいは請願をしているという事実を相手に伝えるために必要なものとして許容される手段の広狭、すなわち「平穏」な請願として許容される範囲には、議会政が閉塞することなくその機能を全うしている場合と比較して自ずから差異が生じるというべきである。
(ウ)そして憲法第16条は「何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」としているのであるから、市民的抵抗について弁第3号証が12頁ないし14頁で摘示する、
① 「市民的抵抗は成熟した民主主義の重要な構成要素である。社会的な目的のために法律を破る市民を国家がどのように扱うかは、確かにその国の政治文化をよく表している」という指摘、
② 「disruptive(秩序攪乱的)であることこそ、こうした市民的不服従の行動の有効性の核心を構成していることをどう考えるか」という指摘、
そして
③ 「政府がデモ参加者に対して、受動的で破壊的でない許容可能な方法を指示することには、まさにそのようなやりかたには効果がないことが実証されているだけに、本質的な矛盾がある・・・わたしたちは、具体的な変化をもたらすためには、秩序攪乱と抗議とは手を取り合っておこなわれると認める必要がある。「抗議する権利」は認めながら、抗議が波風を立てることがないよう指示するといった態度は現実的ではない」という指摘は、
いずれも代議制が閉塞し機能不全に陥っている場合における請願権行使のため採られた手段について、それが「平穏」な請願権の行使として許容され「何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」という保障を享有する否かを判断する際の考慮要素あるいは解釈指針としても妥当する。
したがってこのような場合における請願権の行使に際して外形的には刑罰法規の構成要件に該当する手段が採られたとしても、それが請願行為の存在と内容を知らしめるために必要であり、かつ暴力によるものでもなく違法な害悪の告知を伴うものでない限り、それはなお「平穏」な請願権の行使であって違法性が阻却されるというべきである。
⑵ 被告人の本件行為
ア まず被告人によってなされた本件行為に前後した時期においては、オリンピック・パラリンピックの開催強行に懸念・批判の声が多数上げられていたにもかかわらず(原審における弁第2号証、第4号証)、「声を上げても聞こえない振りをされている」(原審におけるT尋問調書12頁)と評される状況にあり代議制が市民の意思を十分に反映せず閉塞状況に陥っていた一方で、公共の電波においては開催賛成派の財界人が大量殺人を称揚する極めて暴力的な言辞を弄する場面を垂れ流されていたことはまだしも(弁第3号証の10頁ないし11頁)、甚だしきは放送法第31条1項においてその経営委員について「公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する」と規定されている日本放送協会はライブストリーミング放送において聖火リレーに反対する市民の声を意図的に抹消するという、代議制、民主政が機能するための前提を歪める偏頗偏向ぶりを発揮するという有様であった(当審の第2回公判調書3頁、原審における鵜飼尋問調書18頁)。
被告人による本件行為がなされた当時において、代議制が閉塞し機能不全に陥っていり、また民主政が機能するための前提を歪める行為が国の監督を受ける報道機関によってなされていたものである。
イ 被告人の本件行為は「東京オリンピック・パラリンピックやそれに関連する聖火イベントの開催に抗議するという被告人の思想・考えを示すため」本件イベントの主催者そして組織委員会に対する請願行為である。
この請願行為にあたって被告人は暴力すなわち人の身体に向けた不法な有形力の行使を用いたものではなく、また人に対して違法な害悪の告知をなしたものではない(仮に暴力を用いあるいは害悪の告知を伴っていたというのであれば、被告人の本件行為は威力業務妨害罪ではなく暴行罪ないし脅迫罪に問擬されていて然るべきであろう)。
ウ さらに被告人は本件行為にあたって人を傷つけることが無いよう留意していた(原審における被告人質問調書4頁、当審の第2回公判調書1頁)。歴史上の市民的抵抗において人的には非暴力であっても、器物にはなんらかのダメージが加えられる事態は少なくなかったところ、被告人の本件行為においては器物損壊すらなく、誰も傷つけないようなきわめて慎重な意図をもってなされている(弁第3号証の11頁ないし12頁)。そうであるから被告人の本件行為による「被害者」であるとされるUもまた「僕も一瞬びくって、びっくりはしたんだと思います」(原審におけるU尋問調書11頁)と供述する程度の影響しか生じなかったことを認めているのである。
エ したがって、被告人の本件行為は請願行為の存在と内容を知らしめるために必要であり、かつ暴力によるものでもなく違法な害悪の告知を伴うものでないのだから、「平穏」な請願権の行使であって正当行為としてその違法性が阻却される。
オ そして弁3号証の12頁において
「サフラジェットの闘いと比較してみましょう。先ほどあげた、1908年6月のデモ行進時、警官たちの暴力に怒ったメンバーが首相官邸の窓を投石によって破りました。この行動には、器物損壊がふくま
れています。このとき2人の活動家は服役しますが、その期間は2ヶ月です。放火については、禁固刑9ヶ月です。この時代のイギリスですら、このような具体的に器物損壊をふくむ行動に対して、その程度の処罰にすぎません。当時の権利意識、とりわけ女性の権利への意識の弱さにもかかわらず、市民がみずからの権利や意志を表明することの重要性が強く認められていたのです。」(下線部は弁護人による)
と指摘されているのであるから、憲法第16条が請願権を明記し、かつ「何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と明確に規定している今日において、被告人の本件行為が憲法の請願権の保障を受けるものとしてその違法性が阻却されるという結論に何ら不合理なところはない。
4 小括
以上のとおり、本件被告人の行為は、「平穏」すなわち相当な手段方法によってなされた請願行為であり、請願権の保障を受けあるいはその保障の趣旨が及ぶ行為であるから、正当行為としてその違法性が阻却される。
5 原判決が被告人による本件行為の違法性について法令の適用を誤ったものであることは、当審における被告人質問からも明らかである。
⑴ 被告人の行為は表現の自由により保障されていること
ア 被告人の事件前の活動
被告人は、以下の理由から、2020年東京オリンピック・パラリンピック(以下、「2020年東京オリンピック」という。)の開催に反対という意見を持ち、反対する意見表明の活動を行ってきた(当審の第2回公判調書の2頁参照)。
① 2020年東京オリンピックがコロナ禍での開催であり、特に緊急事態宣言の下での強行開催であること
② 2020年東京オリンピックは、世界中で開催反対の声があるにも関わらず、マスコミ等は問題を「無観客開催」とするかに収れんして報道していること
③ T証人の証言にもあるように、2020年東京オリンピックは、国、地方自治体、NHK、電通、マスコミ、スパイダーのような小さな企業をも巻き込んだ総力を挙げてのイベントで、開催に反対の声をあげても聞こえないふりをされることが多かったこと
④ NHK映像問題のように、2020年東京オリンピック開催反対の声が報道から意図的にかき消されていること
このため、被告人は、本件が発生する以前にも、2021年6月6日には、東京都武蔵野市吉祥寺で行われた2020年東京オリンピック開催反対のデモに参加し、吉祥寺や東京都国分寺市内で2020年東京オリンピック開催に反対するスタンディングを行っていた。被告人の地元である多摩地区からオリンピック反対の声をあげたいという被告人の思いからである。
被告人の聖火リレーのイベントで爆竹を鳴らすという行為は、主観的に見ても「2020年東京オリンピック開催反対」という政治的な意見の表現行為である。
⑵ 「2020年東京オリンピック開催反対」という政治的意見表明は社会的に相当である意見の表明であったこと
ア 当時の世論について
事件が発生した2021年7月16日当時、世界中で新型コロナウイルスの感染が拡大し、日本国内でも新型コロナウイルスの感染が拡大していた。このため、2021年5月には、日本国政府から緊急事態宣言が発令されていた。そして、日本国内においても2020年東京オリンピック開催に反対という意見が、国民の約80%を占めていた。
元一橋大学の教授で、反東京オリンピック宣言という本に文書を寄せるなど、東京2020年オリンピックの経緯を追っていた鵜飼哲証人も、当時の世論について次のとおり証言している(鵜飼証言13ページ以降参照)。
2020年3月が大変重要な時期となった。同時期に、ギリシャからトーチ(聖火)が日本に到着することとなっていた。しかし、その頃、新型コロナウイルスの感染拡大が急激に深刻化していった。その中で当時の安倍晋三首相は、夏のオリンピックは必ず行う、人類がコロナウイルスに打ち勝った証として完全な形で開催すると発言していた。結果的に2020年3月24日、バッハ会長と安倍首相により、2020年東京オリンピックを1年間延期するという決断が下された。しかし、当時、新型コロナウイルスのパンデミックがどういう性質のもので、どれくらいの期間続くか全くわかっていなかった。1年間延期という判断に全く科学的根拠が伴っていなかった。
そして、2021年に入っても、新型コロナウイルスの感染拡大は収束することはなかった。
2021年1月9日、10日、共同通信の世論調査があり、2020年東京オリンピックを中止した方が良いという回答が34%ぐらい、もう1回再延期した方が良いという回答が40%以上で、合わせると80%を超える人が2021年夏のオリンピック開催に反対していた。
したがって2021年当時、2020東京オリンピックに反対するという意見表明は、社会的に認められた政治的な意見の表明であった。
イ 被告人の行為が事後的にも社会的に相当であると評価されていること
被告人が聖火リレーのイベントで爆竹を鳴らしたことについては、大阪釜ヶ崎の監視カメラ弾圧裁判で逆転無罪を勝ち取ったメンバー、フランスのパリにおいてオリンピックに反対する活動をしているメンバー、アメリカ合衆国のロスアンジェルスでオリンピックに反対する活動をしているメンバーからも支援のメッセージが届いている(当審の第2回公判調書6頁)。
なお、フランスのパリの団体から届いたメッセージは次のものである。
《すでに多くの支援者が指摘されているとおり、オリンピックは「正当性の低落」(酒井隆史氏意見書)に苦しんでいます。東京地裁は非常に重い、懲役一年という判決を、聖火リレーイベントで鳴らされた爆竹に下しました。これが非暴力の伝統にある異議申し立て行動であることは明白です。このような過剰な反応=反動(reaction)は、正当性の低落という負い目の表出なのでは、とすら思えます。
「弁護団・控訴趣意書」の中には、「オリンピック招致については、住民投票が必須とされておらず、一般に市民は、議員や首長の選挙を通じて間接的に意思表示をするしかない」とあります。これは本当にその通りで、住民投票により市民の承認を得て開催された最後のオリンピックは、2010年バンクーバー冬季五輪となります。2010年代に招致希望都市で行われた住民投票では、オスロ(2013年)のみを例外としてすべて「NO」という結果になっているのです。そして2020年代に入るとオリンピック招致をめぐって住民投票が行われること自体がなくなってしまいました。クラクフ(ポーランド)が、ハンブルグ(ドイツ)が、カルガリー(カナダ)が、シオン(スイス)が招致から手をひいたのは、住民投票で反対が上回ったからです。これからオリンピックがパリで、ミラノで、ロサンゼルスで、ブリスベンで開催されるのは、これらの都市において住民投票が行われなかったからです。現在絶賛難航中である2030年冬季大会の開催都市選定において、住民投票によって開催都市が決定されることはまずないでしょう。数々の要求にもかかわらず住民投票を頑なに拒否する現在の札幌市の対応は、何が恐れられているのかを如実に示しています。
1936年ベルリン五輪以降のオリンピックは、何よりもまずメディアイベントです。開催国の新聞・テレビ・ラジオは例外なく翼賛的になります。営利企業であるメディアにとって、自国開催のオリンピックは重要なビジネスチャンスです。何百万ユーロ、極端な場合は米NBCのように何十億ユーロもの放映権を支払う放送局もあります。国際オリンピック委員会(IOC)のプロパガンダがこのように優勢である以上、必然的に直接行動という選択肢が有力なものとなります。
Covid-19によって開催が脅かされてこそいませんが、正当性の低落に苦しんでいるのは一年後に迫ったパリ五輪も同じです。組織委員長のトニー・エスタンゲは、ブラジルや日本に対して実に失礼なことに、「これまでの五輪と違う」と強調することを好んでいます。はたして本当にそうでしょうか? 選手村建設のために移民労働者が強制退去されました。パリ首都圏の野宿者が地方に強制移動させられている、という報道もすでに出ています。首都圏の職業安定所が紹介する職業訓練は「スポーツイベント警備」関連一色となっています。CROUSという公的機関が運営する首都圏の学生寮は、来年の夏にオリンピックのために差し押さえられ、数千人の学生たちが追い出されることが決定しています。建設現場では事故が多発し、労働者1名がすでに死亡しています。またパリ五輪組織委の重職についている人物2名が創業したコンサル会社にすでに家宅捜索が入っているのですが、驚くべきことに同社は2020年まで電通イージス・ネットワークの100%子会社だったのです。
近年IOCが開催希望都市の減少に苦しんでいるのは、このようなオリンピック災害が漠然とではあっても知られるようになったからです。だからこそ希少な開催希望都市で住民投票を行うことはできなくなり、ますます民主主義が蔑ろにされる、というスパイラルが生まれているのです。
このスパイラルはどこかで断ち切られるのでしょうか? それともオリンピックは2030年代になっても猛威を振るい、とり巻くすべてを破壊していくのでしょうか? 温暖化で雪の降らなくなった世界で、冬季オリンピックは人工雪を使って続けられるのでしょうか?
一つだけ確かなことがあります。IOCが自分たちから「もうこんな時代遅れなスペクタクルはやめよう」と言い出すことはまずない、ということです。オリンピックを葬るのは、不服従を貫く人々の仕事となるはずです。そのためには第二、第三、もっと多くの黒岩さん(注:被告人のニックネーム)が必要となります。すべての破壊されたファベーラを、追い出された野宿者を、建設現場での死者を、そして汚職で有罪を食らったIOC委員を思い出すため、もっと多くの爆竹が鳴らされる必要があります。
Fuck the Olympics、ビバ爆竹。
2023年8月10日≫
被告人の行為は、海外でオリンピックの問題に取り組む人たちからも高い評価を得ていた。
なお、子供の保育や障害者の介助という仕事にたずさわりながら、オリンピック反対運動をしてきたT 証人は、被告人の行為を直に目撃した上で、次のような評価をしている(T尋問調書11頁)。
《(被告人が爆竹を鳴らして裁判になっていることについて)不当なのでないかと思っています。というのは、スパイダーのUさんはそんなに怒ってないんじゃないかなと私は感じて、実際クロイワさんを罰したいのは、オリ・パラなんじゃないかというふうに私は感じていて、まあ国を挙げての、地方自治体やらNHKやら電通やらマスコミやら、あるいは大企業からスパイダ―のような小さな企業まで巻き込んでの、総力挙げての、そして全国から警察を集めて、また自衛隊も出てきての、そういう圧倒的な力でオリンピック・パラリンピックが強行されて、それに対して爆竹というのは、余りにも桁違いに小さい、破壊力が小さいと私は感じています。そして、オリ・パラを強行しなければ失われなかった命というのがあると思っていて、コロナ感染患者に対して医療がもうちょっと、オリ・パラをやらずにそちらのほうに注力できれば、死ななかった人がいると私は思っていて、それに比べて、クロイワさん人を傷つけてないし、というふうに思います。》
これが被告人の行為に対する正しい評価である。
被告人は「多くの人たちに支持され、支持されたことは、本当にありがたいことでした。特に見知らぬ人たちから支援の声が上がったことは、本当にうれしかったです。」(当審の第2回公判調書7頁)と証言している。
実際に、本件の公判には、被告人を支援・支持する多くの人たちが傍聴に訪れ傍聴券が配られるほどである。
被告人の行為は、これまで被告人とは面識のなかった人たちからも支持されるものであり、刑事罰が科されるほど強い非難に該当するものではない。これについては、以下で詳しく述べる。
ウ 事後的にも被告人の行為が正しかったこと
被告人が、「オリンピック組織幹部とこの大手企業との贈収賄、あるいは談合、そして元首相の関与疑惑、そして、更にはこのオリンピック招致に向けての官房機密費の流用といった、オリンピックの構造問題が社会的に明らかにされた、認識されたという点では、自分のやった行為、この爆竹というふうな行為は、意思表示は正しかったと思います。」(当審の第2回公判調書7頁)と供述している。
原審の段階でも鵜飼証人が証言するように、2020年東京オリンピックには、予算の爆増、施設の建設に関しての労災、再開発に伴う野宿者の追い出し等々の問題が指摘されていた。
しかし、本件が高等裁判所に係属するようになってから、被告人が指摘するような問題が次々と明らかになった。
① 紳士服大手のAOKIホールディングスと大手出版社のKADOKAWAがオリンピック組織委員会の高橋浩之氏に賄賂を渡していた(贈収賄事件)。
② 2020年東京オリンピックの運営をめぐる入札において談合が行われたとして大手広告代理店の博報堂が独占禁止法違反(不当な取引制限)で起訴された(談合事件)。
③ 石川県の馳知事がオリンピックの招致委に官房機密費が使われたと発言し、大きく報道された(官房機密費流用問題)。
2020年東京オリンピックは多くの不正の上で開催されていた。2020年東京オリンピックに抗議を行った被告人の行為が正しいといえることが事後的に検証されたと言える。
⑶ 被告人の行為に対し威力業務妨害罪を適用することは適用違憲となる
ア 聖火リレーのイベントにおいて、爆竹を鳴らすという被告人の行為が主観的にも客観的に表現の自由により保障されることについては、すでに述べた。
まず、「2020年東京オリンピックに反対する。」という表現行為は、オリンピックという国家が行う大規模なイベントに反対の意思を表明するという点で、政治的な意見の表明であり、表現の自由(憲法21条)の中でも特に保障されなければならない政治的表現の自由に属する。
イ 確かに、「2020年東京オリンピックを開催する」ということは、「民主的」な意思決定により決定された。
しかし、新型コロナウイルスの感染が拡大し、緊急事態宣言が発令されている事態でオリンピックを強行開催するかについては、民主的な意思決定は行われていない。政府は、国民の8割が反対しても2020年東京オリンピックの開催を強行していた。このことからも、2020年東京オリンピック開催反対という意見表明においては、抗議行動が許容されるべき状況であった。
他方、本件で侵害されたとされる法益は、イベントにおいて観客の誘導等を行っていたUの業務である。この点、本件においてUの業務が妨害されたという立証がされていないことはすでに述べた。仮に、威力業務妨害罪を危険犯と解して、同罪を適用した場合は、侵害された法益は「業務を妨害する可能性」となり、その法益の要保護性は低くなる。
ウ 被告人の行った行為の表現の自由としての価値と被侵害法益を比較衡量すれば、表現の自由の価値が優先されることは明らかである。違法性阻却を認めず、被告人に威力業務妨害罪の刑罰を科した場合は、表現の自由を不当に侵害するものとなり、法の適用において違憲となる。
6 まとめ
以上のとおりであり、被告人の本件行為は正当行為(刑法第35条)としてその違法性が阻却される。
したがって原判決は被告人による本件行為の違法性を判断するにあたって法令の適用を誤ったものである。
第4 結語
以上、原判決には事実の誤認があり(本書面の「第1」)、また威力業務妨害罪の構成要件並びに被告人の行為の違法性についてそれぞれ法令の適用を誤ったものであり(本書面の「第2」、「第3」)、これら誤認あるいは誤りはいずれも判決に影響を及ぼすことが明らかである。
したがって、原判決を破棄し直ちに被告人に対して無罪の判決を言渡すことが相当である。
以 上